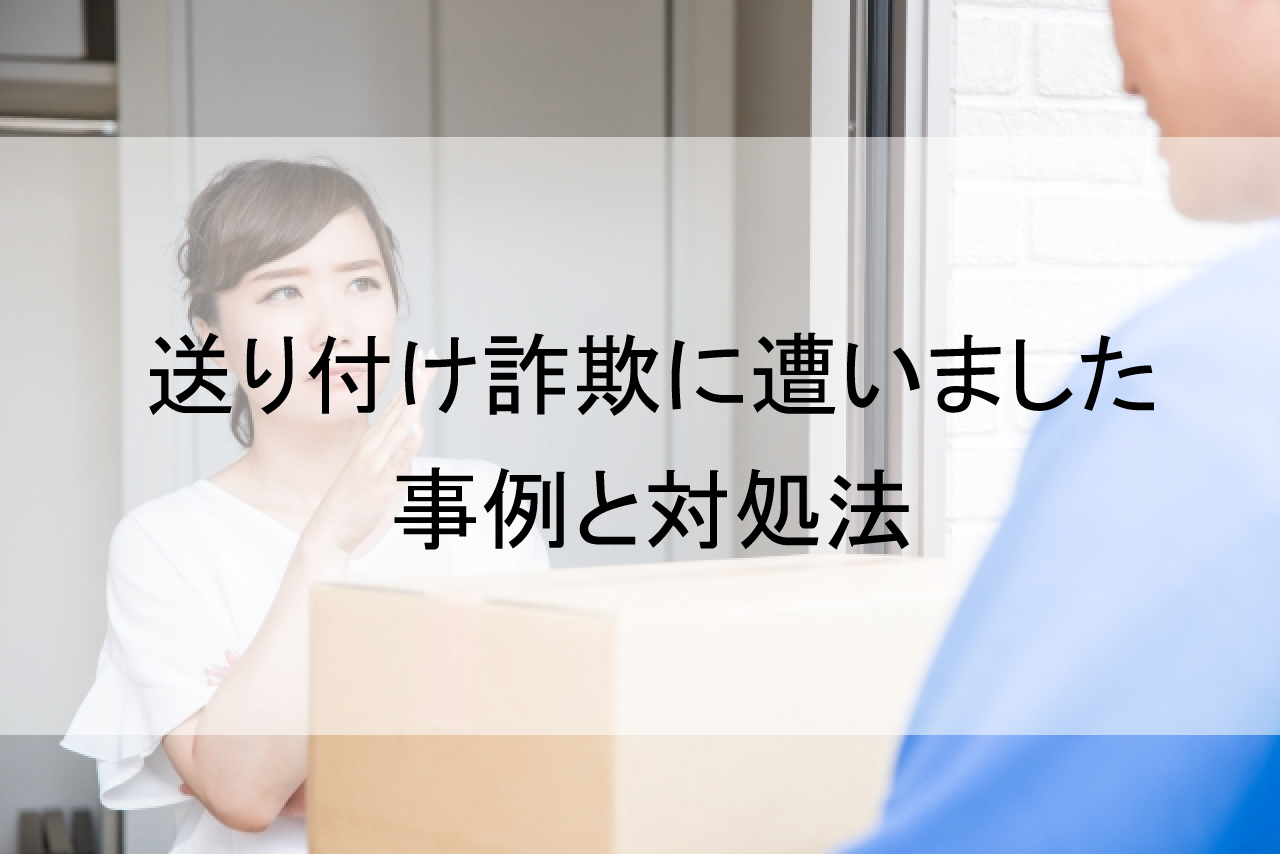本日、送り付け詐欺を初めて体験しました。
幸い受け取ることなく持ち帰ってもらえましたが、平穏な日常にいきなり入ってきた巷の手法に
終わった後にドキドキしてしまった事案です。
送り付け詐欺の事例としての話と対処法をまとめます。
送り付け詐欺で受け取り拒否をした話
夏のお昼時で家には私と夫の二人でした。インターホンが鳴って対応すると
「郵便局です。〇〇さん(夫の名前)宛に代引きの荷物です。」
画像にも郵便局らしき車が映っています。「代引きです」のセリフに「(夫から)聞いてないけど?」と思いつつ印鑑を持って外に出ました。
荷物は「米麹で作った甘酒」とダンボールに書いてあります。あて名は夫になっていました。
「名前にお間違いありませんか?」
「はい。主人の名前ですが…」
郵便局員に「主人は代引きで買い物をした覚えがないと言ってます」と伝えると
「受け取り拒否ということでいいですか」とさくっと聞かれましたので
「はい」
すると郵便局員は短冊のように束になっている紙を取り出し
「お客様は(あて名の)ご主人様ではないので代理人の欄に印鑑を押してください。」
その細長い紙には「受け取りを拒否します」と書かれてありました。
送り付け詐欺に騙されないための対処方法

私と夫は普段から 注文して何か届きそうなときには互いに報告をしています。
「数日中にブックオフから荷物が届くから」
「ヤマトから荷物が届くことになっている」
「代引きで化粧品を買ったから、お金を封筒に入れて玄関に置いておくね」
遠方の親戚に久しぶりに会いに行ったときは、その後ねぎらいの品物が送られてくることがあります。
お葬式の香典返しもありますね。
予測のつく荷物は夫婦で共有することによって、一人の時も対処が可能です。実は今回、夫は明日出かける用がありました。
今日でなく明日で不在の時だったら、こんなにスムーズに受け取り拒否ができたかわかりません。
テレビCMで有名なアディーレ法律事務所が送り付け詐欺についてサイトでまとめています。

「代引き」はまだわかりやすい送り付け詐欺です。「代引きじゃない」場合もあります。2年前に法が改正されて、受け取ってしまった荷物もすぐ処分して大丈夫になっています。
絶対にやっていけないのは、この2点です。
- 連絡先に電話をしてしまう
- 代金を払ってしまう
法が改正されても代引きで支払ってしまったお金が戻ってくることは、まずないそうです。
最初から払わないことが鉄則になります。
送り付け詐欺で受け取り拒否をした話 まとめ
ネット通販が生活の中で身近になり、週に何度も荷物が届くというのは当たり前なことになっています。
送り付け荷物が「代引き」であれば、そうでないかどうかは家人に確認すれば すぐわかります。
今回の送り付け詐欺では、宛先がどこだったのか確認するのを忘れてしまいました。
夫が言うには、去年登録していた先で個人情報が漏洩したというニュースがあったとのこと。
私も使っている家電の会社で漏洩があり、お詫びとして500円分のクオカードをもらったことがあります。
名簿はどこに渡っているかわかりません。荷物の受け取りには最新の注意をした方がよさそうです。